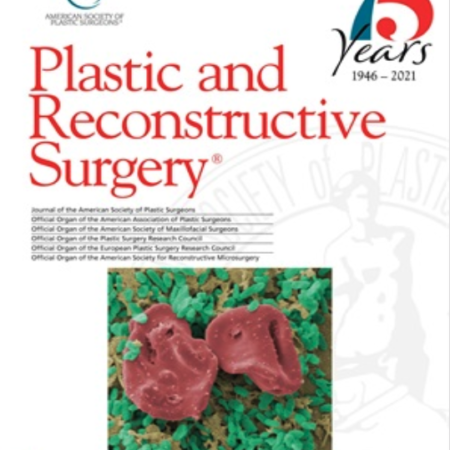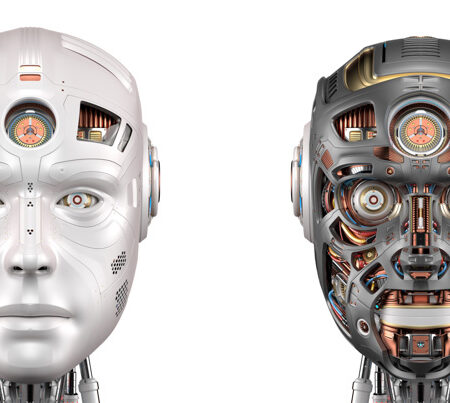それって プロフェッショナル?

先日 診察中に患者さんに聞かれた.
「前のクリニックでは ガイコツのモデルと作るって言われたんですけど,センセイは作らないんですか?」
「いや プロなら,お顔を診ただけでわかるから 要らないでしょ・・・」と言いそうになるのをこらえ
「えっっと・・ あなたくらいの左右差であれば CTデータだけでわかるので 要らないっていうか・・ もちろん作ることもあるけど もっと超絶に歪んでる方のときくらいですね・・」とだけ返答した.
もっと正直に言えば,「経験値を正しく積めば モデルはだんだんと不要になる.ただのエラ削りなんかでいちいちモデルを作ってるのは まだまだ修行中のレベルか よっぽどセンスがなくて モデルがないとできないアマチュアなんじゃね」ですわ.
誤解してほしくないので言うのだけれど,モデルの価値はよく知っているし,それを否定するつもりはない.今でも複雑な三次元変形であったり 教育目的の場合は モデルを作る.なぜなら アタシ自身,1990年代にモデルの開発に関わる研究をしていて,その真価はよくわかっているからだ.
当時,今で言う三次元プリンターの先駆けのような 光硬化樹脂造形が登場し,これをCTデータを使って活用しようという試みがあった.東大時代にクラニオ関係を専門にしていたこともあって,東芝メディカルさんと組んで5~6年開発に当たった経緯がある.
ちょっとその頃を思い出しちゃったのだが,それはそれは 大変な作業だったわ.
まず今のような ヘリカルCTでなかったので,そもそもスライスデータを2mmで撮るのに,1時間以上もかかった.(今は,ほんの数分)
患者さんはその間 あのトンネルのなかで じっとしていなくてはならず大変だったし,ちょっとでも動いてしまうと データ座標がズレるので 絵がちょん切れてしまう,なかなか厄介な作業であった.
それにもまして たいへんだったのが データの処理.
スライスデータはA3くらいのサイズの 巨大な光ディスクに収めてあって それを東芝の研究所のコンピュータに持っていって読み込ませ,作業する.100枚以上のスライスデータを処理して 三次元画像を作成するのに,なんと1時間かかった.
しかも三次元画像をカットして,蝶形骨の形状を確認しようとかすると それだけでまた20分ほどかかる・・・
もちろん モニターの前でじっと待っているだけなので やることはないので 論文とかを読みながら待ってる.
ひとりの患者さんのデータを処理するのに 半日かかる.そんな時代だった.
光樹脂造形は,そのデータを渡して作成してもらうので,実務はなかったが,それでも30時間以上はかかっていた.
だから,はじめてガイコツのモデルを手にしたときは ほんとうに驚いた.
こんなことができるんだ・・まさに 手に取るようにわかるじゃないかっ! と感動したわ.
それからは,研究費を使って なんでもかんでもモデルを作ってた.(当時製作費1個20万!)
でも 10個ほど作成したころから,全部の症例には要らないんじゃないか って感じ始めたんだわ.
もちろんモデルがすごく役に立つ場面というのがあるのは 間違いないんだけど,モニターで見る3次元画像である程度は状況がわかるようになってきた.要するに 2次元表示の「絵」と3次元の「実体」とが 頭でリンクできるようになってくるんだわ.
もちろん こうなるためのプロセスにはモデルが必要であって,そういう意味での価値はあったと言える.
今は 歪みがひどくて正中軸を決めにくい症例くらいしか作らない(美容外科領域ではね)
だから もしプロの美容外科医を名乗りたいなら エラでモデル作るのをを卒業してからにしてほしいわね.せめて
まあ でもナビが頼りのタクシードライバーも少なくない時代だから
仕方ないのかねぇ・・